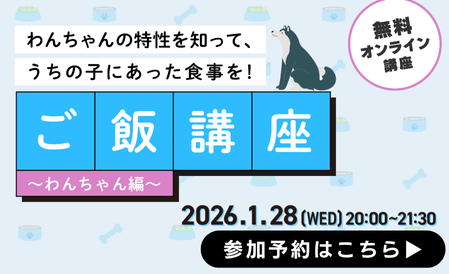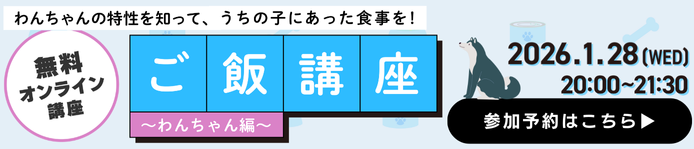ゴールデン・レトリーバーはイギリスを起源とする大型犬で、優しく穏やかな性格と、ふさふさとした美しい被毛が特徴です。家庭犬としてだけではなく、盲導犬や介助犬としても広く活躍し、世界中で高い人気を誇る犬種です。賢く愛情深い一方で、関節や熱中症などに注意が必要な面もあります。この記事では、ゴールデン・レトリーバーの特徴や性格、かかりやすい病気、飼い方のコツについて詳しく解説します。
目次
ゴールデン・レトリーバーの歴史

ゴールデン・レトリーバーは、もともとイギリスで鳥猟の補助犬として発展したと考えられていますが、その正確な起源や歴史については明らかになっていません。ルーツにはさまざまな説がありますが、1865年にスコットランドの愛犬家が手に入れたウェービー・コーテッド・レトリーバーの子犬が始まりとされています。
その後の交配では、アイリッシュ・セターやニューファンドランドなどの犬種の血が加わったともいわれています。かつては「イエロー・レトリーバー」と呼ばれていましたが、1920年に現在の「ゴールデン・レトリーバー」という名称に統一されました。
ゴールデン・レトリーバーの特徴

ゴールデン・レトリーバーは、豊かでやわらかな被毛に加え、首やお尻、しっぽに見られる飾り毛が特徴の美しい犬種です。
主に2つのタイプがあり、イギリス系は丸みのある頭部と低めの耳を持ち、クリーム系の毛色が多く、穏やかで家庭犬に適しています。一方、アメリカ系はスレンダーな体型で、赤茶やゴールドなどの濃い毛色や、長めのマズルが特徴的で、活発で好奇心旺盛な性格の子が多いといわれています。
体格の目安としては、オスが体高56~61cm・体重29~34kg、メスが体高51~56cm・体重25~29kg程度です。
ゴールデン・レトリーバーの性格

ゴールデン・レトリーバーは、穏やかで感受性が豊か。まわりの空気を読むのが得意です。子どもや小型犬、子犬と遊ぶ時には自然と力を加減し、相手に合わせて優しく接することができます。
飼い主への愛情も深く、家族との信頼関係を築きやすいのも大きな魅力のひとつです。また、賢くて飲み込みが早いため、しつけがしやすい点も人気の理由。盲導犬や介助犬、麻薬探知犬として活躍することも多く、学ぶ力の高い犬種として知られています。
ゴールデン・レトリーバーのかかりやすい病気

ゴールデン・レトリーバーには、遺伝的にかかりやすい病気がいくつかあります。ここでは、飼う前に知っておきたいゴールデン・レトリーバーがかかりやすい主な病気について解説します。
胃捻転症候群(いねんてんしょうこうぐん)
胃が拡張とねじれを起こす急性の病気で、大型犬に多くみられます。過食やドライフードや穀物主体の食事、過度な空気の飲み込み、過食などが原因として考えられます。食後数時間で発生し、死亡率が高い病気です。
【症状】
腹部が膨張して嘔吐のしぐさを繰り返すものの何も吐かず、呼吸が苦しそうな様子が見られます。そのまま処置を受けなければ、ショック状態に陥って最悪の場合死に至るケースもあります。舌や歯茎などの粘膜が紫に変色し、腹部の左側が急激に膨らんできた場合は、至急診察を受けましょう。
【診断】
触診やレントゲン検査、血液検査などを通じて行われます。
【治療】
口からのチューブ挿入または皮膚の上から注射針を胃内に刺してガスを排出します。同時にショックの治療として、大量の輸血とともに副腎皮質ホルモン製剤や抗生物質を投与します。
大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべんきょうさくしょう)
ゴールデン・レトリーバーに多発する病気で、遺伝性と考えられています。主な原因は、大動脈弁下の繊維性の狭窄で、左心室流出路近くに線維組織を合併することがあります。
【症状】
多くは無症状ですが、狭窄の程度によっては興奮時の虚脱や失神が見られます。軽度であれば治療を必要としないこともありますが、中程度以上の例では、二次的に左心室の肥大が起こり、肥大した心臓に十分な酸素を運搬できなくなって突然死を起こすことがあるので注意が必要です。
また、急に運動したり興奮したりした時に、不整脈が発生したり、心臓から十分な血液が送り出されずに失神することもあります。
【診断】
大型犬では、初回の混合ワクチン接種時には認められなかった典型的な収縮期性の心雑音が、数カ月後のワクチン接種時や健康診断時に発見されることがあります。心電図やX線検査では左心室の肥大が示唆され、心エコー検査によっておおよその重症度を診断することが可能です。
【治療】
軽度であれば、飼育管理に十分注意しながら、進行を防ぐ薬を与えて内科的治療を行い経過を観察します。重症になると突然死のリスクが高まり、長期生存が難しくなります。心臓カテーテル検査後にバルーンカテーテル治療を試みたり、重篤な場合には外科的治療をしたりすることもあります。
心臓腫瘍(しんぞうしゅよう)
ゴールデン・レトリーバーは血管肉腫を発症しやすい犬種とされており、特に心臓にできる腫瘍は悪性であることが多いです。発症の多くは中年齢から高齢にかけてですが、若い犬でも発症することがあります。
【症状】
初期にはほとんど症状が現れません。特有の症状はなく、進行すると呼吸困難や不整脈などの心不全の症状、全身の衰弱などが見られるようになります。
【診断】
X線検査や心電図検査、心エコー検査、造影検査などが診断に有効です。必要に応じてCT検査やMRI検査が行われることもあり、腫瘍の種類を確定するためには生検が必要です。
【治療】
残念ながら、長期的な生存が可能となる確実な治療法はほとんどありません。腫瘍の場所や大きさによっては手術が可能な場合もありますが、抗がん剤治療や放射線治療を選択しても完治は難しく、主に症状の緩和や延命を目的とした治療が中心となります。
重症筋無力症(じゅうしょうきんむりょくしょう)

先天性と後天性がありますが、ゴールデン・レトリーバーでは後天性の発症が多く見られる傾向があります。
神経の末端から放出される「アセチルコリン」という物質が筋肉に届いても、それを受け取る受容体が免疫異常によって減少してしまい、神経からの信号がうまく筋肉に伝わらなくなることで筋力が低下する病気です。1~3歳、9~13歳の年齢層でよく発生します。
【症状】
運動によって筋力低下が悪化し、休息によって改善するのが特徴です。流涎、吐出、嚥下困難、瞳孔散大、眼窩下垂、鳴き声の変化、虚脱などの症状が見られます。
【診断】
塩化エンドロホニウムを用いたテンシロン検査、血液中の抗アセチルコリン受容体抗体の検出、筋電図検査などによって診断します。ゴールデン・レトリーバーに多い後天的な重症筋無力症は、胸腺腫や肝臓がん、肛門嚢腫瘍、骨肉腫、皮膚型リンパ腫、原発性肺腫瘍などに伴って発生することがあるため、これらとの鑑別診断も必要です。
【治療】
薬による内科的治療が基本ですが、腫瘍が原因となっている場合には、例えば胸腺腫であれば摘出手術を行うこともあります。
甲状腺機能低下症(こうじょうせんきのうていかしょう)

甲状腺から必要な量のサイロキシンが分泌されなくなることで起こる病気です。甲状腺が変性していく自己免疫性疾患と考えられており、遺伝的な要因も関与しているとされています。
性別による差はありませんが、避妊・去勢手術を受けた犬に多く見られる傾向があります。また、副腎皮質機能亢進症などの別の病気が原因で発症した場合は、元の病気の治療によって甲状腺機能が正常に戻ることもあります。
【症状】
激しい運動を嫌がるようになり、散歩でもすぐに満足して帰ろうとする様子が見られます。目つきやしぐさに覇気がなくなり、異常に寒がりになり、暖房のそばから離れない、夏でも日の当たる窓辺を好むといった行動も特徴です。
被毛にも変化が表れ、毛換えがなくなったり、大腿部の後ろや両側の脇腹の毛が抜けたりすることがあります。また皮膚炎が起きたり、歩き方が不自然になったりすることもあります。これらの変化は加齢の影響と見なされやすく、飼い主が気づきにくいこともあります。
【診断】
体のさまざまな部位に症状が現れるため、診断が難しい病気です。疑わしい場合は甲状腺ホルモンの測定を行い、症状や血液検査の結果、ホルモンの数値などを総合的に判断して診断します。
【治療】
合成甲状腺ホルモン製剤を投与して、低下した機能を補います。薬は経口投与が可能で、自宅での治療が可能です。治療は生涯にわたって継続する必要がありますが、薬の効果によって多くの症状は改善されます。
股関節形成不全(こかんせつけいせいふぜん)
股関節の発育不良により、成長とともに関節の変形や炎症が進行する病気です。関節の緩みや脱臼、亜脱臼が起こることがあります。
【症状】
通常は生後4~12カ月頃に症状が確認されますが、2~3歳になるまで気づかないこともあります。腰を振るような歩き方をする、走る時にうさぎ跳びのように後肢が同時に地面を蹴る、坂道の途中で座り込む、階段の昇降や運動を嫌がる、後肢を引きずる、起き上がるのが困難になるといった症状が見られます。
【診断】
触診を含む身体検査とX線検査によって診断されます。
【治療】
症状の程度や年齢、X線検査の結果、費用、飼い主の希望などを総合的に判断して治療方針を決定します。治療法には、運動制限や鎮痛剤、体重管理によって関節の保存を目指す保存的治療と、手術による外科的治療の2種類があります。
肘突起癒合不全(ちゅうとっきゆごうふぜん)
肘形成不全の一種で、成長期に発生します。肘の骨の一部である肘突起が、正常に癒合しないまま成長することで起こる病気です。急速な成長や遺伝的素因、未成熟な骨への外傷などが原因と考えられています。
【症状】
歩き方に違和感がある、肘を痛がるなどの症状が見られますが、進行が緩やかなため、2~3歳になるまで気づかないこともあります。
【診断】
触診やX線検査によって診断します。
【治療】
内科的治療としては鎮痛剤の投与を行います。外科的治療では、癒合していない肘突起の切除が一般的です。
筋ジストロフィー(きんじすとろふぃー)
骨格筋が進行性に変性し、筋力が低下していく遺伝性の病気です。
【症状】
筋肉が弱っていくことで、運動を嫌がるようになったり、筋肉量が減少したりするなどの変化が見られます。全身の筋肉が徐々に衰えていくため、飲み込む力が落ちて食事がしにくくなったり、呼吸が困難になることもあります。
【診断】
血液検査や筋電図検査、筋肉の生検など、複数の検査を組み合わせて診断します。
【治療】
現在のところ、完全な治療法はない為、痛みの緩和を図る対症療法が中心です。また、運動制限や体重管理などにより、関節や筋肉への負担を軽減することも重要です。
アトピー性皮膚炎(あとぴーせいひふえん)
腹部や顔、手足、わきの下などに炎症が起き、強いかゆみを伴う皮膚の病気です。およそ半数の犬が外耳炎を併発するとされ、正確なメカニズムは明らかになっていませんが、近年アトピー性皮膚炎と診断される犬は増加傾向にあります。
【症状】
1~3歳で発症するケースが多く、1歳未満での発症は少ないとされています。ほとんどの場合でかゆみがあり、初期には皮膚の発赤や脱毛が見られ、慢性化すると皮膚の肥厚や色素沈着、脂漏、紅斑などが進行します。ブドウ球菌やマラセチアといった菌の感染により、症状が悪化することもあります。
【診断】
発症年齢と皮膚の症状から診断されます。ただし、アトピーと食物アレルギーが同時に存在しているケースもあるため、鑑別が必要です。
【治療】
シャンプーで皮膚の汚れや余分な脂分を洗い流し、皮膚を清潔に保ちます。。症状の軽減には、副腎皮質ホルモン製剤や抗ヒスタミン薬などを使用します。完治は難しく、長期的な管理が必要です。
悪性繊維性組織球腫(あくせいせんいせいそしききゅうしゅ)
線維(結合)組織や筋肉の深い部分にできる悪性腫瘍で、進行が早いのが特徴です。
【症状】
腫瘍ができる場所によっては歩行困難、痛みが出る、食欲が落ちるなどの症状が現れます。進行とともに体重が減り、衰弱していきます。
【診断】
臨床所見とバイオプシー(組織検査)によって診断されます。
【治療】
残念ながら、有効な治療法は確立されていません。
ゴールデン・レトリーバーの育て方

犬のしつけは、飼い主はもちろん日々の暮らしをスムーズにする大切なステップです。特にゴールデン・レトリーバーは賢く、人との信頼関係を大切にするため、丁寧で一貫性のあるしつけが効果的です。ここでは、子犬期から成犬までの育て方のポイントを簡潔に紹介します。
子犬の時からしつけ教室などを用いる
体格がどんどん大きくなっていくゴールデン・レトリーバーは、焦って飼い主が無理にしつけようとするよりも、「しつけ教室」などを活用して、早めから段階的に取り組むことが大切です。家族との信頼関係が深くなる犬種だからこそ、1匹でも安心して過ごせるように、落ち着いて休める環境づくりやしつけも欠かせません。
家族のために何かをしたいという本質をうまく活用する
ゴールデン・レトリーバーは、生まれつき「家族と共同作業がしたい」という気持ちを強く持っている犬種です。そのため、日常生活の中に遊びや簡単なお手伝いなどを取り入れてあげることで、心が満たされ、ストレスの解消や問題行動の予防にもつながります。
ゴールデン・レトリーバーの飼い方

穏やかな性格で人との暮らしに向いているゴールデン・レトリーバー。快適に過ごすためには、住環境の工夫や日々のケアが欠かせません。ここでは、暮らしやすい環境づくりのポイントと、必要なケアについて紹介します。
滑らないよう床を工夫する
ゴールデン・レトリーバーは大型犬で体重もあるため、滑りやすい床は関節に大きな負担をかけてしまいます。特に年齢を重ねて筋肉量が落ちてくると、フローリングでは踏ん張りがきかず、転倒やケガの原因になることもあります。
ペット用の滑りにくい床材に替えたり、マットやラグを敷くなど、足腰を守る工夫が大切です。また、寝る場所にはクッション性のあるベッドを用意し、肘や膝に床ずれができないよう配慮しましょう。
遊びを取り入れながら運動をしっかりさせる
ゴールデン・レトリーバーは体力が豊富で活発な犬種のため、毎日の運動が欠かせません。理想は1日2回、各30分以上の散歩を行うことです。可能であれば、ドッグランなどで自由に走らせる時間も確保しましょう。
もともと水鳥の回収作業をしていた犬種なので、何かを探して持ってくる遊びが大好きです。ボール遊びや宝探しのようなゲーム、水遊びなどは、本能を満たしながら運動不足の予防にもなるため、積極的に取り入れたい遊びです。
毎日ブラッシングする
ゴールデン・レトリーバーはダブルコートの被毛を持ち、抜け毛が多いため、毎日のブラッシングが欠かせません。特に春から夏にかけての換毛期は抜け毛が増えやすく、放っておくと毛が絡まりやすくなります。
毛先から少しずつ優しくブラッシングし、もつれがある部分は指でほぐしてから整えるのがポイントです。全体を整えたあとにコームで毛並みに沿ってとかすと、さらに美しく仕上がります。定期的なケアを続けることで、毛玉の防止や皮膚トラブルの予防にもつながります。
熱中症に注意する
ゴールデン・レトリーバーは被毛が二重構造(ダブルコート)になっているため、熱がこもりやすく、夏は熱中症に注意が必要です。
特に湿度が高いと体温調節がうまくできず、体調を崩しやすくなります。室内では呼吸が荒くならない程度の温度を保ち、エアコンや除湿機を活用して快適な環境を整えましょう。散歩は気温が下がる朝や夕方の時間帯を選び、直射日光を避けることも大切です。
ゴールデン・レトリーバーについて理解を深め楽しく暮らそう

優しく穏やかな性格で、世界中から愛されているゴールデン・レトリーバー。家族として迎えるなら、その特徴やかかりやすい病気、日々のケアについて理解しておくことが大切です。愛情と向き合う気持ちがあれば、一生のパートナーとして心強い存在になってくれるでしょう。ゴールデン・レトリーバーについてよく知り、家族に迎えてみてはいかがでしょうか。

福山 貴昭 博士