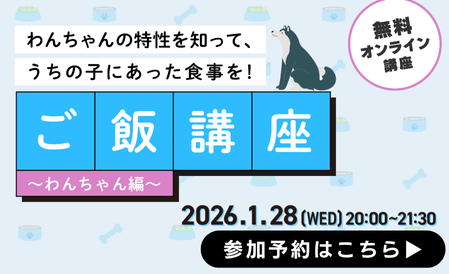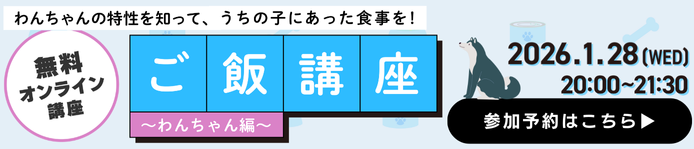ふわふわの毛並みや大きな目が愛らしいポメラニアン。愛玩犬として高い人気を誇る犬種ですが、飼育の上で押さえておきたいポイントも複数あります。今回はポメラニアンの飼育を検討している人に向け、犬種の歴史や特徴、性格、かかりやすい病気、飼育の注意点などを解説します。
目次
ポメラニアンの歴史

ポメラニアンは、サモエドなどのスピッツ族を小型化した犬種です。ドイツのポメラニア地方に土着していた種類で、もともとの大きさは中~大型でしたが、小型に改良され現在のような大きさに。19世紀にイギリスへ渡り、ビクトリア女王の愛犬として一気に注目を集め、そこから人気が高まり世界中で親しまれるようになりました。
ポメラニアンの特徴

体高は雄・雌ともに18~22cmほど、雄・雌ともに理想的な体重は1.8~2.3kgです。頭、体、足は小さいですが、全身がふわふわのダブルコートの被毛に包まれていることから、独特のボリューム感をもっています。豊かなアンダーコートに支えられるようにして、皮膚に対して垂直にオーバーコートが生えていて「スタンド・オフ・コート」と呼ばれます。認められている被毛の色は10種類以上です。
<代表的な被毛の色>
オレンジ、レッド、ウルフ・セーブル、ブラック、ブラック・タン、ブラウン、クリーム、ホワイトなど
ポメラニアンの性格

ポメラニアンは明るく、好奇心旺盛で活発な性格です。特に飼い主になつきやすく、甘えん坊なところがあります。また飼い主の考えを理解する賢さももっています。他の犬や生物とも良好な関係性を築くことが可能です。ただし注意深い性質があるため、知らない相手には強い警戒心を見せ、吠えやすい傾向も見られます。
ポメラニアンのかかりやすい病気

次に、ポメラニアンがかかりやすい病気について解説します。
変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
関節軟骨が変形して痛みを伴う病気です。痛みが生じるため関節を動かさなくなると、さらに凹凸が生じて関節の変形が進むという悪循環に陥ります。またこの病気は、加齢とともに進行します。
【症状】
関節に凹凸ができるため、歩くと痛みが生じます。歩き方に異常が見られたり、階段の上り下りや高いところからジャンプするのを嫌がったりします。また、凹凸が生じた関節の腫脹や可動範囲の減少、関節運動に伴ってギシギシと音を立てる捻髪音(ねんぱつおん)、関節の不安定症がみられます。
【診断】
X線検査で診断します。
【治療】
症状に基づいて運動制限や体重制限、非ステロイド性抗炎症剤の投与を行います。必要な場合は、基礎疾患の外科治療を行うことがあります。
膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)
膝のお皿(膝蓋骨)が正常な位置からずれてしまう病気で、パテラ脱臼とも呼ばれます。なお、パテラとは膝蓋骨のことです。
【症状】
歩き方に異常が見られ、足をかばうような動きをします。また高い場所からジャンプを避ける様子もあります。
【診断】
X線検査で診断します。
【治療】
原因治療は膝のお皿を正常な位置に戻す外科手術ですが、必ずしも手術で完治を目指せるとは限りません。高齢の犬では、軟骨の摩耗などにより、手術が難しいこともあります。その場合は、関節疾患の薬による治療を行います。
膝蓋骨脱臼について詳しく解説した記事も参考にしてください。
Vet’s Advice! 犬の関節炎【膝蓋骨脱臼編】
動脈管開存症(どうみゃくかんかいぞんしょう)
先天性の心臓病で、大動脈と肺動脈とをつなぐ動脈管という血管が遺残する病気です。
【症状】
初期に症状が見られることはありません。重症になると、運動するとすぐ疲れる、咳、吐く、倒れる、呼吸困難、食欲がない、体が大きくならないなどの症状が見られます。末期になると、心臓の位置より後ろ側(しっぽ側)の皮膚や粘膜が紫色になる分離チアノーゼを起こします。
【診断】
聴診、心エコー検査によって診断します。初回のワクチン接種時に動物病院で発見されることが多い病気です。
【治療】
治療をしない場合、1歳まで生きられる確率(1年生存率)が約30%と、死亡してしまう確率が非常に高い病気です。急速に進行するため、診断がついた時点で速やかに手術を行います。予後は良く、一般的な寿命が迎えられます。
気官虚脱(きかんきょだつ)
気管が本来の強度を失いつぶれてしまう病気で、原因は解明されていません。気管は加齢とともに弱くなることから高齢犬に多く発生しますが、ポメラニアンやチワワなどは遺伝的な要素も指摘され、若齢でもよく見られます。また、高温多湿の環境や興奮、ストレスなどによって悪化しやすい傾向にあります。
【症状】
「ガーガー」というアヒルが鳴くような声が特徴的です。興奮時や運動後に激しくなることがあり、また咳、咳の後の吐き気などがあります。これらの症状は高温多湿、興奮、ストレスなどで悪化しやすく、多くは次第に悪化していきます。
【診断】
症状とX線検査の結果に基づいて診断します。
【治療】
急性症状の改善を目指す内科的治療が行われますが、根本的な治療には外科手術が不可欠です。最近は気管を広げるための装着材(プロテーゼ)に、特殊なアクリル材を加工したものが用いられるようになり、手術時間の短縮と長期的な治癒が実現されつつあります。
睫毛乱生(しょうもうらんせい)
本来、睫毛(まつげ)は外向きに生えるものですが、睫毛が内向き(角膜)に向いて生える状態を睫毛乱生といいます。睫毛が角膜に触れることで、眼にさまざまなトラブルを引き起こします。
【症状】
睫毛が角膜を刺激することで、涙眼になったり、角膜が傷ついたり、さらには角膜潰瘍を起こすことがあります。
【治療】
異常な睫毛を切除したり、再発を防ぐために毛根を電気で焼いたりします。
流涙症(りゅうるいしょう)
本来、涙は涙点という目頭にある小さな穴から鼻涙管(びるいかん)を通って鼻へと排出されます。しかし涙が目頭(内眼角)から溢れてしまう状態を流涙症といいます。原因としては涙液分泌の増加や、涙液の排泄障害、涙嚢炎(るいのうえん)などの隣接する病巣が考えられます。先に紹介した睫毛乱生も、涙液の分泌を増加させる原因のひとつです。
【症状】
涙が常に眼から溢れているように見え、眼の周囲の被毛が濡れた状態になります。また周囲の被毛は、溢れ出た涙液と反応して赤茶色に変色します。
【治療】
涙液の増加や隣接病巣によるものは原因疾患を治療し、排泄障害の場合は涙管洗浄を行います。
乳歯遺残(にゅうしいざん)
犬の歯は、人と同じように乳歯から永久歯に一度だけ生え変わります。しかし、歯が生え変わる時期(一般的に生後6~7カ月)を過ぎても乳歯が残っている状態を乳歯遺残といいます。犬の場合は、乳犬歯と乳切歯が残ることが多い傾向にあります。
【症状】
永久歯と乳歯が密に存在するため、歯垢や歯石が沈着しやすく、歯周病に進行しやすいです。乳歯の遺残する部位により、正常でない噛み合わせである不正咬合を起こすこともあります。
【治療】
乳歯遺恨が見つかったら速やかに乳歯を抜歯します。
白内障(はくないしょう)
眼の中のレンズ(水晶体)が白く濁り、光に対する感覚が鈍る病気です。犬の白内障は、多くが老化によるもので、7歳を過ぎた頃から水晶体に混濁が出始めます。老齢性白内障は、犬種を問わず加齢とともに起こります。また、糖尿病性白内障といった全身疾患に関連して起こるものや、眼の病気に併発するもの、薬物やケガで起こる白内障があります。
【症状】
眼が白く見え、常に瞳が広がっているように見えるのが特徴です。視力が衰えて暗い場所でものが見えにくくなります。そのため暗い場所で動かない、壁伝いに歩くなど視覚障害を示す症状が現れます。
【診断】
瞳孔を開かせる薬を点眼し、スリットランプと呼ばれる細い光を眼に当て、角膜や水晶体を観察する検査を行います。
【治療】
目薬や飲み薬による内科的治療、手術による外科的治療があります。視覚障害や失明している場合は手術が必要です。手術によって白く濁った硝子体を取り出したり、眼内レンズに置き換えたりして視力の回復を目指します。
白内障について詳しく解説した記事も参考にしてください。
犬の白内障とは? 発症パターンやリスク、治療法について解説【獣眼科医 監修】
脱毛症X(だつもうしょうえっくす)
別名アロペシアXとも呼ばれます。雄に多く発生する脱毛症で、去勢・避妊前に症状が現れることが多いです。副腎性のプロゲステロン過剰症、アンドロゲン過剰症が原因と考えられています。成長ホルモン反応性皮膚症、性ホルモン関連性皮膚疾患といわれることもあります。
【症状】
四肢と頭部を除く部位で左右対称の脱毛が見られます。患部は完全に脱毛しますが、羊毛状の毛が残ることもあります。毛が抜けた場所の皮膚には、フケや色素沈着が認められることがあります。
【診断】
血液検査、生化学検査を行います。また甲状腺や副腎の機能性検査を行い、甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症との鑑別を行います。
【治療】
去勢していない場合は、去勢手術を行います。去勢後に発症した場合は、患部を完全に脱毛し、成長ホルモンやメチルテストステロンを投与します。治療により被毛は生えてきますが、その後、換毛期に再び脱毛することがあります。
ポメラニアンの育て方

犬のしつけは、飼い主はもちろん日々の暮らしをスムーズにする大切なステップです。
無駄吠えをしないようトレーニングを行う
ポメラニアンは警戒したり興奮したりすると吠えることが多いので、これをしつけで対応したいところです。子犬の頃から家族以外の人や他の犬と触れ合う機会をもち、警戒心を抱く必要がないものには吠えないよう教えていきます。インターホンの音でも吠えることがあるので、そちらもトレーニングが必要です。
小型犬種のため、歯磨きや爪切りなどのケア作業も非常に細かい作業となります。そのため”安心して身を委ねる、全身をリラックスして触れさせる”トレーニングをしておくことも重要です。
スキンシップや遊びの中でトレーニングする
気が強くわがままになってしまうことを避けるためにも、日々の生活の中で「アイコンタクト」や「待て」を覚えさせましょう。
ポメラニアンの飼い方

最後に、ポメラニアンの飼育上のポイントを紹介します。ポメラニアンの体質や性格を踏まえながら、犬にとって快適な環境を整え、適切なお世話をしましょう。
定期的に丁寧なブラッシングを行う
ポメラニアンの飼育でとりわけ注意したいことのひとつがブラッシング。毛が長く毛量も多いダブルコートをもつため、抜け毛が生じやすくなります。美しい毛並みをしっかり維持できるよう、日々丁寧なブラッシングを行いましょう。頻度は週2回を目安にしてください。
換毛期は特に抜け毛が大量になるので注意です。またブラッシングで毛を抜きすぎると特徴である毛のボリューム感が失われてしまうので、ピンブラシなど被毛を抜きすぎないブラシの使用がおすすめです。
涙やけの対策や口腔ケアを行う
涙やけができやすいので、目ヤニや溢れた涙をこまめに拭き取って清潔にしましょう。口内環境が悪くなりやすいので、毎日の歯磨きや半年に1度の歯科検診がおすすめです。
足に負担がかからないよう気を付ける
ポメラニアンは関節トラブルが多い犬種です。足に大きな衝撃や負担がかかるとケガ・疾患などにつながりやすいので注意が必要です。例えば室内に高い場所があるとそこに上り、飛び降り・落下などをして足腰を痛めることも。高所に上らせない工夫や、できる限り段差を少なくする工夫などをすると良いでしょう。
フローリングはカーペットやマットを敷き滑りにくくするのも有効です。また歩き方がおかしかったり、さわって痛そうにしたり、様子に不安がある場合はすぐ病院へ相談してください。
適切な食事と運動を心がける
ポメラニアンのような小型犬には、粒が小さくて飲み込みやすいフードが適しています。フードと水のみで必要な栄養をバランス良くとれる総合栄養食がおすすめです。
関節トラブルへの配慮が必要なこと、豊かで美しい被毛を守るために、骨や関節の健康をサポートする成分や皮膚・被毛をすこやかに保つ成分を多く含んだフードを検討しても良いでしょう。小食や偏食のポメラニアンも多いので、おやつの与えすぎには注意して運動をしっかり行うことも大切です。
ポメラニアンについて理解し、家族に迎える準備をしよう

ポメラニアンは小柄な体に活発な性格をもつ活動的な犬種。警戒心の強さやデリケートな足腰に注意を払いながら、適したお世話・しつけを行っていきたいですね。飼い主に強い親しみをもつポメラニアンはきっと素敵な家族になってくれるでしょう。ぜひポメラニアンに関する知識を深め、お迎えを検討してみてください。

福山 貴昭 博士