メインクーンは「ジェントルジャイアント(穏やかな巨人)」と呼ばれるほど体が大きく、セミロングの豪華な被毛が特徴の猫。性格は温和で人懐っこく、かわいらしい鳴き声も魅力です。かかりやすい病気や、お世話で注意したい点など、メインクーンを家族に迎える前に知っておきたいポイントを解説します。
目次
メインクーンの歴史
メインクーンは、1800年代にアメリカ北東部・メイン州の港町に暮らしていた土着の猫と、船で運ばれてきたアンゴラやノルウェージャンフォレストキャットなどの長毛種との交配によって誕生したといわれています。
ブラウンタビーの被毛や大きな体、ふさふさした尾の特徴から、「アライグマ(ラクーン)との交雑種ではないか」という伝説が生まれ、「メインクーン」という名前がつきました。名前の由来にもなった極寒のメイン州でたくましく生き抜くために、骨太で筋肉質、長くがっしりとした体を備えた猫種です。
メインクーンのかかりやすい病気
メインクーンは遺伝性疾患を含め、以下のような病気に注意が必要です。定期的な健診で早期発見につなげましょう。
肥大型心筋症(ひだいがたしんきんしょう)
肥大型心筋症は、猫で最も多く認められる心臓の病気で、左心室心筋の肥大が特徴です。5~7歳での発症が多く、雄で多く見られます。人と同様に、遺伝が関係している場合もあります。多くの場合が無症状です。
-
●診断
聴診、X線検査、心電図検査、心エコー図検査などにより診断します。 -
●治療
病態によって4つのステージに分類され、それぞれのステージに合わせた内科治療を行います。
腹膜心膜横隔膜ヘルニア(ふくまくしんまくおうかくまくへるにあ)
腹膜心膜横隔膜ヘルニアは、横隔膜の欠損孔を介して心膜腔と腹膜腔が交通(※)し、腹腔内臓器が心膜腔内に逸脱する先天性の奇形です。欠損孔の大きさにより逸脱する臓器が異なり、さまざまな臨床症状が現れます。
※交通:医学用語でつながっていることを意味します。
-
●診断
X線検査や超音波検査によって診断します。 -
●治療
臨床症状があり、若齢で発見された場合は外科的治療が望ましく、適切に行われれば予後は良好です。臨床症状がなく、逸脱の程度および臓器の機能障害が軽度な場合は、無治療で経過観察することもあります。特に高齢まで無症状で経過している場合には、経過観察とされることが多くあります。
歯周病(ししゅうびょう)
歯周病は、歯垢の蓄積によって引き起こされる歯周組織の細菌感染による炎症性疾患です。糖尿病や肝疾患などの全身疾患とも関連し、口腔内の問題にとどまらず、全身の健康管理の一環として治療を考える必要があります。
-
●診断
猫は警戒心が強く、口に触れることを嫌がるため、問診や口腔内以外の身体検査を先行することが重要です。顔つきの変化、目の下やあごの下が腫れたり、鼻汁や鼻血、よだれによる前肢の汚れなどを観察します。口腔内以外の検査を終えた後、口腔内の検査を経て最終的な診断をします。 -
●治療
まずは歯科処置や対症療法から開始し、反応が乏しい場合には積極的に抜歯手術を検討します。ホームデンタルケアが可能かどうかが、治療方針や予後に大きく影響します。
腸重積(ちょうじゅうせき)
腸重積は、重度の腸炎や異物、腫瘍などを原因として発生する病気です。嘔吐、腹痛、食欲の減退といった症状が認められます。
-
●診断
臨床症状の確認に加え、腹部の触診や超音波検査などを用いて診断します。 -
●治療
多くの場合、外科手術による整復や切除が必要です。
多発性嚢胞腎(たはつせいのうほうじん)
最終的に、両側の腎臓に複数の嚢胞を有する遺伝性疾患です。腎嚢胞は年齢とともに数が増え、嚢胞内には尿とは異なる液体が貯留して徐々に大きさを増していきます。正常な腎組織を圧迫するため、最終的には腎機能不全に陥ります。
-
●診断
遺伝子検査での診断が可能です。また、超音波検査によって嚢胞の存在を確認します。 -
●治療
遺伝性疾患のため根治は望めず、腎不全に対しては投薬治療によって機能をコントロールします。
子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)
子宮蓄膿症は、子宮壁に生じる急性または慢性の化膿性炎症です。犬ほど多くはありませんが、猫でも発生します。発情兆候から約4週間以内に発症することが多く、典型的な臨床症状として、陰部からの排膿、発熱、食欲不振、元気消失などが見られます。
-
●診断
陰部からの捺印細胞診、腹部X線検査、超音波検査、血液検査などを組み合わせて診断します。 -
●治療
一般的には外科療法(子宮・卵巣摘出術)が行われます。全身性炎症反応症候群や子宮破裂による腹膜炎がなければ、予後は良好です。子宮摘出を希望しない場合には、内科治療を選択することもあります。
脊髄性筋萎縮症(せきずいせいきんいしゅくしょう)
脊髄性筋萎縮症はメインクーンに特異的な遺伝性疾患で、発症に性差はなく、通常は生後3~4ヵ月齢で発症します。四肢の筋虚弱や萎縮が見られ、特に後肢の症状が重度です。進行は8ヵ月齢頃からゆるやかになる傾向があります。
-
●診断
品種や臨床症状、血液化学検査などを総合して診断します。 -
●治療
遺伝性の病気であるため根治的な治療法はありません。筋虚弱の程度には個体差があり、成長後も四肢で歩行可能な場合がある一方、重度の場合には前肢のみでの歩行となる症例もあります。
股異形成(こいけいせい)
股異形成は、犬で頻繁に認められる整形外科の病気ですが、猫でも時折発生します。寛骨臼の浅化と変形性関節症の発症に関連があるとされ、遺伝性病気と考えられています。特に純血種の猫で多く見られるのが特徴です。
-
●診断
触診およびX線検査によって診断します。 -
●治療
股異形成と股関節の変性関節症に対して、保存療法(安静の徹底、疼痛管理、体重管理)や、外科手術(大腿骨頭骨頸切除術や股関節全置換術)を行います。
大腿骨頭すべり症(だいたいこつとうすべりしょう)
大腿骨頭すべり症は、「自然発生性大腿骨頭成長板骨折(しぜんはっせいせいだいとうこつとうせいちょうばんこっせつ)」とも呼ばれ、大腿骨頭骨端部と大腿骨近位骨幹端の間にある成長板で骨端軟骨の閉鎖が遅れ、ケガをしていないのに骨折のような状態が起きる病気です。
去勢雄での発生が多く、通常は1~2歳で発症します。早期の去勢や肥満による成長板への過剰な剪断力(せんだんりょく)が、リスク要因とされています。
-
●診断
臨床症状の確認や触診、X線検査によって診断します。 -
●治療
保存療法(疼痛管理と安静の徹底)、大腿骨頭骨端部の整復・安定化、または大腿骨頭骨頸切断術が行われます。症例の状態に応じて治療法を選択します。
第Ⅰ因子欠乏症(だいいちいんしけつぼうしょう)
第Ⅰ因子(フィブリノゲン)と呼ばれる、肝臓でつくられるタンパク質の異常により起こる病気です。重症度によっては出血傾向が見られますが、メインクーンでは出血傾向がなくても凝固因子(血を固める成分)の低下や異常がある場合があります。若齢期に外科手術を受けたりケガをした時に、出血が止まりにくくなることで発見されることが多い病気です。
-
●診断
血小板数の減少を伴わない出血が見られる場合、凝固線溶系試験、凝固因子活性測定、交差混合試験などを用いて診断します。 -
●治療
この病気は生涯にわたって付き合っていく必要があります。特に外科手術の前には必ず血液がきちんと固まるかを調べる凝固検査を行い、遺伝性の凝固因子欠乏の可能性を追求します。
血友病A(けつゆうびょうA)
血友病Aは、外科手術後や外傷を負った際の異常出血をきっかけに発見されることが多い病気です。メインクーンでは、明らかな出血傾向がなくても第XI因子が低下していたり、凝固因子に異常がある場合があります。
-
●診断
血小板数の減少を伴わない出血が見られる際に、凝固試験を行って診断します。 -
●治療
多くの場合は、新鮮血漿、新鮮凍結血漿、クリオ製剤の投与を用いた治療を行います。生涯にわたるコントロールが必要な病気です。
食物アレルギー性皮膚炎(しょくもつあれるぎーせいひふえん)
食物アレルギー性皮膚炎は、特定の食べ物を摂取した際にかゆみを伴う皮膚炎です。どの年齢でも発症する可能性がありますが、比較的若齢での発症が多く見られます。
-
●診断
症状と食歴から疑い、他の痛痒性病気を除外したうえで、厳密な除去食試験および負荷試験を行って診断します。 -
●治療
確実な診断が得られた場合は、食事療法のみで良い結果が期待できます。除去食を食べてくれなかったり、食事だけでは効果が出ない場合には、薬を使った治療を行います。
中耳のポリープ(ちゅうじのポリープ)
中耳のポリープは、鼻咽頭(びいんとう)ポリープや炎症性(えんしょうせい)ポリープとも呼ばれ、中耳、耳管、鼻咽頭の粘膜上皮から発生する非腫瘍性のポリープとされています。通常は片側に生じますが、まれに両側に見られることもあります。
原因は明らかではありませんが、特にメインクーンに多く、1歳以下で発見されることが多いとされています。発生に関与する遺伝子は、現時点では特定されていません。
-
●診断
耳鏡検査やX線検査、CT検査などで診断し、確定診断にはポリープを切除して病理組織学的検査を行います。 -
●治療
ポリープは内視鏡または外科的に切除します。内科療法のみでは効果が期待できません。再発する可能性もあるため、適切な外科的対応と経過観察が必要です。
皮膚肥満細胞腫(ひふひまんさいぼうしゅ)
皮膚肥満細胞腫は、猫において皮膚腫瘍の中で2番目に多く見られ、主に頭頚部の皮膚に発生します。病変の大きさは2ミリ程度から30ミリ以上までさまざまです。経過とともに腫瘤の大きさが縮小と増大を繰り返すことがあります。
-
●診断
病理組織学的検査や細胞診によって診断します。 -
●治療
第一選択は外科手術で病変を摘出することです。摘出後、再発や転移が見られなければ予後が期待できます。
メインクーンとの生活で気を付ける点

メインクーンは体が大きいため、十分な生活スペースや体格に合った生活用品を用意することが大切です。また、日々のお世話で注意すべき点もしっかり確認しておきましょう。
大きな体格に合わせた環境を用意する
メインクーンは大型種のため、広い生活空間が必要です。トイレや食器なども、体格に合った大きめのサイズを選ぶようにしましょう。生活スペースには障害物を減らすといった環境づくりの工夫も必要です。十分に体を動かせる広い場所で遊ぶことで、メインクーンはより楽しく健康的に過ごせます。
また、室内で飼育する場合は、滑りやすさを防ぐために足裏のタフト(飾り毛)を刈ると良いでしょう。自宅で刈るのは難しいため、動物病院やトリミングサロンで処理してもらうと安心です。
1日2回のブラッシング、コーミングを行う
毛玉の予防には、こまめなブラッシングやコーミングが欠かせません。特に長毛のメインクーンには、朝晩1回ずつ、1日2回のお手入れが理想的です。習慣づけることで抜け毛の飛散や皮膚トラブルの予防にもつながります。
メインクーンを飼うのに向いている人

野生的な外見とは裏腹に、非常に温和な性格を持ち、「ジェントルジャイアント」とも呼ばれるメインクーン。無邪気で遊び好きな一面もあるため、一緒に遊ぶ時間をしっかり取れる人に向いているといえるでしょう。
メインクーンを家族に迎えようと考えている方へのメッセージ
メインクーンの特性を知って家族の一員に迎え入れよう

大きな体、なめらかな被毛、温和な性格など、メインクーンはたくさんの魅力を持った猫です。家族として迎えるなら、体のサイズに合わせてゆとりのある生活スペースを確保してあげてください。また遺伝性の病気があるため、定期的に健診を受けて早期発見につなげることが大切です。
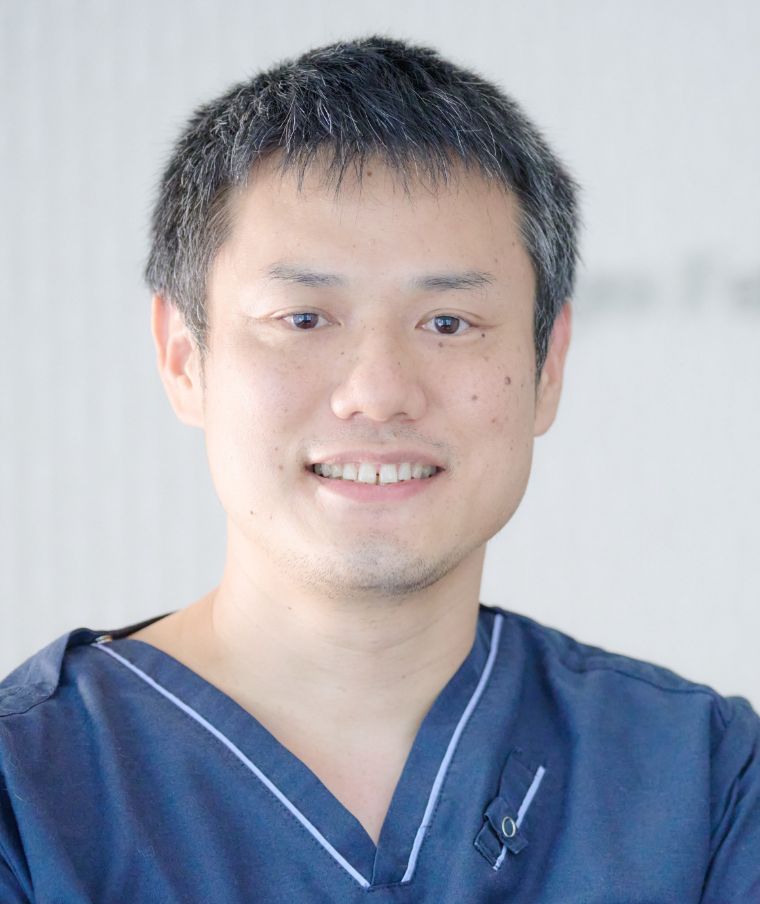
服部 幸 先生








